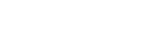来場セミナー
オンラインセミナー
【来場型/Webセミナー(ライブ配信)同時開催】
労働法実務マスターコース
パートタイム・有期雇用労働法の改正を踏まえた
有期・無期・短時間契約社員、派遣社員等に関する法律と実務
~最新動向への対応策と今後の有期・無期契約労働者の活用、正社員との差異のあり方~
日付
日時
10:00 〜 17:00
受付終了
会場案内
来場会場
三井住友銀行呉服橋ビル
東京都中央区八重洲1-3-4
会場のご案内はこちら
オンラインセミナー
本講座は、それぞれインターネットに繋がる場所(職場・ご自宅等)から
パソコン等の端末よりご参加いただくオンライン講座です。
※受付は30分前より開始いたします ※欠席・遅刻の場合は、必ずご連絡をお願いいたします ※会場は当日1F掲示板にてご確認ください ※本セミナーは、「労働法実務マスターコース」→https://www.smbc-consulting.co.jp/smbcc/seminar/business/details/BusinessAndFlatRateSeminar/2022/10/20220090-01.htmlのカリキュラムに設定されております ※セミナータイトル変更 : ≪変更前≫有期社員・無期社員・契約社員等に関する法律と実務 ●ライブ配信のお申込みページの公開は開催月の1~2か月前となります。 ●満席でお申込みできない場合でも、オンラインセミナー(ライブ配信)ではお申込み可能です。 ●オンラインセミナー(ライブ配信)のお申込みはこちら https://shop.deliveru.jp/hr/law/pch1ruab/?__ac=oY1Z056-YJ9Us ●本セミナーはSMBCコンサルティングが提携するDeliveruサイト(株式会社ファシオ提供)からお申込みいただきます。 ・Deliveruにログインまたは会員登録(無料)の上、お申込みを行ってください。 ・お申込完了後、Deliveruにログインし、ご視聴いただきます。 ・詳しくは、Deliveruのお申込みページをご確認ください。
概要(狙い)
非正規社員をめぐる実務においては、同一労働同一賃金の原則のもと、不合理な待遇格差解消への取組みが求められています。さらに正規と非正規の待遇格差に関する注目すべき裁判例も出てきており、各企業の実態に応じた対応を検討していかなければなりません。 本セミナーでは、法的解説もさることながら、今日の企業を取り巻く環境から、有期・無期契約労働者や外部労働力を利用するときに人事・労務担当者として押さえておくべき点を解説します。人事や総務部門だけでなく、現場において派遣会社や業務受託会社と契約交渉をする担当者にもご参加をおすすめします。
対象者
人事・総務・法務・内部監査部門等担当者
講師

弁護士
丸尾 拓養 氏
略歴:東京大学法学部卒。大手コンピューターメーカー勤務後、弁護士登録。労働事件(使用者側)を専門とする。リストラ・メンタルヘルス・賃金引き下げ等の法律相談への対応のほか、解雇・過労死等の訴訟への対応も行う。また、実務的視点からのセミナーや管理職研修等を行う。
著書:「近年の最高裁判決が人事実務に投げかけるもの」(2020年10月労務行政研究所、「企業競争力を高めるこれからの人事の方向性」所収)、「コロナ禍が変える雇用のあり方の現実」(「BUSINESSLAW JOURNAL」2020年8月号)、「実務視点で読む最近の労働裁判例の勘所(令和4年上期)」(「労政時報」4044号-22.10.28)など
到達目標
◎非正規社員をめぐる法律の基本と実務の留意点を網羅的に理解できる ◎パートタイム・有期雇用労働法、労働契約法、派遣法のしくみなどの法制の最新動向を理解できる ◎有期・無期契約労働者、短時間労働者等、これからの労働者のあり方を考えることができる
プログラム
1.有期・理解するための視点 1)雇止めが認められるには差異のある「働かせ方」が重要である 2)無期転換は新しい段階に入っている 3)最高裁は「同一期待同一賃金」といった 4)「定年退職した労働者である」ことが差異を根拠づける 5)正規雇用がなくなれば非正規雇用がなくなる 2.有期契約労働者(1) -「期間満了で終了」と「5年超で無期転換申込権発生」- 1)雇止め法理(労契法19条) <1>有期労働契約と期間の定めのない労働契約 <2>反復更新の効果 <3>解雇権濫用の類推適用 <4>実質的に無期と異ならない場合 <5>「雇用継続への期待の合理性」 <6>雇止めできる場合、できない場合 <7>「更新の有無・理由」の明示 <8>有期労働契約の締結、更新及び雇止めをめぐる基準 <9>労働条件通知書と個別契約書 <10>均等法・育介法の「不利益取扱い」 <11>最近の裁判例の傾向の変化(河合塾事件東京地裁判決) 2)無期転換 <1>5年超で無期転換の申込権 <2>無期転換後の労働条件 <3>クーリング期間 <4>無期転換の例外 <5>実務 3.有期契約労働者(2)-「賃金処遇」の不合理性 1)「同一労働同一賃金の原則」の正しい理解 2)均衡待遇と均衡処遇 3)「不合理な労働条件の禁止」(パートタイム・有期雇用労働法) 4)「差別的取扱いの禁止」(パートタイム・有期雇用労働法) 5) 短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針 (旧:同一労働同一賃金ガイドライン) 6)最近の裁判例 ●メトロコマース事件ほか2020年10月最高裁判決 ●長澤運輸事件ほか2018年6月最高裁判決 7)手当、基本給、退職金の相違はいかなる場合に不合理とされるか 8)説明義務 4.短時間労働者 1)不合理な労働条件の禁止 (パートタイム・有期雇用労働法8条) 2)差別的取扱いの禁止 (同法9条) 5.高年法再雇用 1)継続雇用制度の導入 2)対象者基準 3)更新基準 4)労働条件 5)定年前の労働条件との相違の不合理性 6)65歳までと70歳までの雇用の相違 7)最近の裁判例 6.労働者派遣 1)派遣法の仕組み 2)有期雇用派遣 <1>事業場単位の期間制限 <2>労働者個人単位の期間制限 <3>特定行為 3)無期雇用派遣 4)4つの違反と直接雇用申込みみなし 5)偽装請負 6)有期/無期雇用派遣とパートタイム・有期雇用労働法8条・9条 7)派遣元労使協定方式と派遣先均等均衡方式 8)最近の裁判例
受講料
SMBC経営懇話会 特別会員
税込 30,800円
SMBC経営懇話会 会員
税込 35,200円
それ以外の方
税込 39,600円