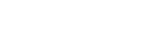来場セミナー
人事・労務をめぐる法律や制度は目まぐるしく変化。担当者に必要な知識をセミナーでキャッチアップ!
人事・労務基礎マスターコース(上期)【全4講】
労働法、社会保険・労働保険、給与計算、人事制度の重要ポイントを1日で学ぶ
各講 選択受講可
日付
会場案内
※受付は30分前より開始いたします ※欠席・遅刻の場合は、ご連絡をお願いいたします
概要(狙い)
人事・総務・労務部門担当者の方を対象として、特に新任者・初心者の方におすすめのコースです。労働法、社会保険・労働保険、給与計算、人事制度の4つの視点から、人事・労務の基礎知識を網羅的に習得します。 【第1講】 昨今、労働法の分野では目まぐるしく法改正がなされ、最高裁で重要な判決も出ております。総務・人事・労務・法務担当者としては、関連する労働法を広く押さえているか否かで、実務の対応の良し悪しが大きく左右されます。 そこで本セミナーでは、実際の企業で問題となっている事例を交えて、労働法の基礎を説明いたします。また、最新の法改正のポイントも解説いたしますので、ぜひご参加ください。 【第2講】 社会保険は、病気やけが、高齢化、介護、失業等の将来起こりうるリスクに対して備える公的保険制度です。人生のさまざまな場面で関わりがありますが、そのしくみをご存知ですか? 会社では、年間の定例業務のほか、社員の入退社、病気やけが、出産育児などイベントごとに手続きが必要で、ミスや届出漏れがあってはなりません。 本セミナーでは、初めて社会保険・労働保険の事務を担当される方、しくみを学びたい方、初任者を指導される管理職の方を対象に、採用から退職までの各種手続き・主な給付の内容・事務手続きのポイントなどを、最新の法改正を踏まえながら具体例を交えてわかりやすく解説いたします。 【第3講】 毎月必ず行われている給与計算は、間違いがなくて当然、もし間違いがあれば人事担当者の信用問題にもなりかねない大切な業務です。最近は、給与計算ソフトが充実しており、数字の意味や算出方法の知識がなくても正しく処理を行えるようになりましたが、担当者の知識が不足していると、結果の確認が正確に行われないなど思わぬミスにつながります。さらに、労働基準法や健康保険法といったさまざまな法律をベースに処理を行いますので、法律の最新知識を常にアップデートしておく必要があります。 本セミナーでは、給与計算に関する基礎的な法律知識を初めての方にもわかりやすく解説し、簡単な実習を交えて給与計算実務を習得していただくことを目的にしております。給与計算業務に不安をお感じの方におすすめいたします。 【第4講】 今の人事制度ができて長い年月が過ぎているとしたら、制度疲労を起こしている可能性があります。なぜならば近年の社会変化は、会社の戦略と従業員の働き方を大きく変えてしまっているからです。人事制度とはそもそも戦略達成のために変化をさせるべきものです。なぜなら、新規事業を立ち上げたい、イノベーションを起こしたい、コストを下げながら売り上げを伸ばしたい。そんな思いを共有し行動するためのマネジメントツールだからです。 本セミナーでは、最新の改革事例を踏まえ、人事の本質を示します。等級、評価、報酬の各制度とその関係性を理解することで、人事の担当から経営者まで自社への適用の方向性を学んでいただけます。ぜひご参加ください。
対象者
人事・労務担当者で基礎能力を身につけたい方
講師

岩谷・村本・山口法律事務所
弁護士
村本 浩 氏
主な取扱分野:訴訟、企業・労働法務、個別的労働関係紛争・団体的労使紛争への助言・代理、労務コンプライアンス意見書作成、労務デューデリジェンスなどに従事 略歴:京都大学法学部卒業後、京都大学法科大学院に進学、大学院卒業後、司法試験に合格。2007年弁護士登録し弁護士としての道を歩む。2008年1月北浜法律事務所・外国法共同事業に入所、2009年6月経営法曹会議入会、2015年1月に独立し、村本綜合法律事務所を開設。2016年には、岩谷・村本・山口法律事務所に事務所名を変更。多数のセミナー・講演を行い、大阪労働局幹部職員に対するコンプライアンス研修、豊中市医師会産業医研修会、各都府県社労士会研修会などの講師を務める。

あかね社会保険労務士法人
代表社員
山中 晶子 氏
主な得意分野:労務相談、就業規則作成・改訂支援、人事制度策定・運用支援 略歴:大学卒業後、大手総合電機メーカー人事部に勤務した後、実父が経営者であるドラッグストアチェーン人事部にて勤務し、管理部門全般を担う。在職中に社会保険労務士試験に合格し、2009年にあかね社会保険労務士法人(旧よつば社会保険労務士事務所)を設立。中小企業経営者の家庭に生まれ育ち、自身も経営者側の立場から、人事・労務に携わった経験をもつ。中小企業の実態を踏まえたコンサルティングが強み。

社労士事務所 Partner
代表
西本 佳子 氏
主な得意分野:給与計算、年末調整、社会保険手続き、労務管理、人事制度 略歴:都市銀行や生命保険会社勤務後、会計事務所で「経理・給与・年調」のアウトソーシング業務を担当。平成17年より社労士事務所開業、給与計算・年末調整は20年以上実務を継続中、併せて平成21年より10年以上給与計算関係セミナーを継続中、累計受講者数4,000人以上。 主な登壇セミナー:「はじめての給与計算と社会保険の基礎セミナー」「はじめての年末調整実践塾」「給与計算品質向上セミナー」「給与計算実務能力検定試験対策講座(1級)(2級)」「給与計算実務能力検定試験模擬試験講座(1級)(2級)」

セレクションアンドバリエーション株式会社
代表取締役
平康 慶浩 (ひらやす よしひろ) 氏
略歴:グロービス経営大学院准教授も兼ねる。早稲田大学大学院ファイナンスMBA。外資系コンサルティングファーム、シンクタンクを経て独立。「わかりやすい人事評価制度」「使いこなせる人事評価制度」を目指し、中堅・中小企業から大企業まで数多くの人事評価制度を構築している。マネジメント力を引き上げる考課者研修、リーダーシップを高める管理職研修も数多く実施。労働市場やキャリア構築のあり方について日々、雑誌やブログなどで情報発信している。
著書:「7日で作る新・人事考課CD-ROM付」(明日香出版社)など
到達目標
【第1講】 ◎労働法の基本を幅広く網羅的に理解できる ◎労務問題に対応するための重要ポイントが理解できる ◎法改正や判例など、最新の動向への対応ポイントが理解できる 【第2講】 ◎社会保険・労働保険のしくみが理解できる ◎社会保険・労働保険の正確な手続きができる ◎社会保険・労働保険の最新の知識が身につく 【第3講】 ◎給与計算ソフトに頼らず、給与計算ができる知識が身につく ◎時間外手当の計算が正しくできる ◎保険料の計算や徴収の仕組みがわかる ◎所得税の算出方法が理解できる 【第4講】 ◎戦略にあわせた人事制度設計の基礎が理解できる ◎人事制度のあるべき姿について説明できるようになる ◎具体的な人事制度改革の方向性を示せるようになる
参加者の声
【第1講】 ・最新の判例、法改正の動向を踏まえた内容だったこと、実務上、重要な部分を詳しく説明いただいたことが役に立ちました ・弁護士さんということで労働問題に関する役立つ知識をたくさん聞けてよかったです ・条例や判例だけでなく実務上の具体例なども話して頂いて、分かりやすかった ・今ある知識+αで最新の事象も説明いただいたので、理解が深まった ・実務上判断に迷う時などに参考にできると思った ・1から学ぶとたくさんになるところを要点をまとめていただき勉強になりました ・しっかりと準備をして臨めば紛争はある程度未然に防げるのだと自信になりました 【第2講】 ・実務上の確認ポイントを説明していた点や気をつけるポイント、社保と労働保険の違いを説明していた点がよかった ・社会保険の知識がゼロでしたが、実際にあった例を使って説明してくださったので、とても分かりやすかったです ・実務に使えるポイントをご紹介くださっているため、業務での活用がイメージしやすかった ・よくある質問として私が聞きたいことを質問する前に全て説明してくださった ・特に理解もせず社会保険に携わっていたので、仕組みがわかり勉強になった ・今後雇用保険に関わる仕事をする予定なので今回のセミナーは参加できてよかった ・今まで不明な点を都度調べながら業務を行なっていたため、自信を持って取り組めると思います 【第3講】 ・給与計算の流れや基本的な事項を学ぶことができ、実務に活かせると思った ・法改正部分も網羅されており、今後の業務の参考になりました ・テキストを常にデスクの上において、日々の業務にあたりたいと思うくらい充実していた ・給与計算ソフトに頼っており不安な部分があったが、計算ロジックを知ることができ業務への自信がついた ・実際の給与明細のロジックが理解できたので、実際の業務内で説明できると思います ・実務に沿った分かりやすい説明で理解しやすいと思いました ・実際に計算したり、分かりやすい言い回しで教えて下さったので頭に自然と入りました ・給与計算の具体的手順について職場でも活用できると思った。後で見直すときに活用できると思った 【第4講】 ・人事評価制度を刷新する必要性を感じていたので、道しるべとなるセミナーでした ・今期、制度改革をするにあたり何をどのように変えていくか立案のヒントになった ・他社事例やアドバイスがあり、わかりやすかった ・各項目で具体的な話をしていただいたのでわかりやすかった ・今後の人事制度改革に役立つと思った ・ワークで自社の問題、課題について考えることができてよかった ・人事制度立案の軸(会社が求める人物像)が何か、明確にする必要があると気づけた ・新しい人事制度構築に大変役立った
プログラム
【第1講】 1.募集・内定・試用・採用 1)募集・採用の注意点 2)採用内定の注意点 3)試用期間の注意点 4)紛争事例の紹介~本採用拒否の落とし穴~ 2.労働条件の設定と変更(賃金を中心に) 1)就業規則はなぜ必要か? 2)就業規則の不利益変更 3)賃金の支払に関する4原則 4)退職金の注意点 5)紛争事例の紹介~退職金の減額・不支給の落とし穴~ 3.労働時間・休憩・休日・年次有給休暇 1)労働時間・休憩・休日の注意点 2)未払い残業代問題と労基署対応 4.人事権・懲戒権 1)配転の注意点 2)出向・転籍の注意点 3)懲戒権の行使 5.労働契約の解消 1)「解雇権濫用の法理」の厳しさを再認識する 2)退職勧奨・希望退職の募集 3)整理解雇の進め方 6.有期雇用者 1)中途解約・雇止めをめぐるリスク 2)有期雇用者の労務管理の注意点 7.労働者派遣 1)労働者派遣契約の概要 2)派遣労働者の労務管理の注意点 8.ハラスメント 1)裁判所におけるハラスメントの認定手法 2)ハラスメント被害の申告があった場合の対応 【第2講】 1.社会保険制度のあらまし 2.労災保険のしくみ 1)労災保険の対象者 2)保険料の計算 3)労災保険の特別加入 4)業務災害と通勤災害 3.雇用保険のしくみ 1)雇用保険の被保険者 2)保険料の計算と徴収 3)入社・退社の際の手続き 4.労働保険料の申告と納付 1)年度更新の手続き 5.健康保険・厚生年金保険のしくみ 1)健康保険・厚生年金保険の被保険者 2)扶養家族の範囲 3)保険料の計算と徴収 4)入社・退社の際の手続き 6.給付のしくみと手続き 1)労災保険の給付 (1)労災保険の給付の種類(病気やけが、休業など) (2)それぞれの給付のしくみ 2)雇用保険の給付 (1)雇用保険の給付の種類(失業や休業など) (2)それぞれの給付のしくみ 3)健康保険の給付 (1)健康保険の給付の種類(高額の治療や休業など) (2)それぞれの給付のしくみ 4)厚生年金保険の給付 7.出産・育児にかかわる給付と手続き 1)給付のしくみ 2)保険料免除制度と手続き 8.人事担当者が知っておきたい周辺知識 1)日本の年金制度 2)マイナンバー制度 【第3講】 1.給与計算業務の全体像について 1)給与計算の年間スケジュール 2)給与計算の月間スケジュール 3)給与計算の手順 4)給与システム設定 5)給与システム社員登録 6)給与計算に必要な知識と情報 2.労働時間等の適正な把握をしよう(勤怠項目) 1)法定労働時間と所定労働時間の違い 2)所定労働日数 3)法定休日と所定休日の違い 4)振替と代休の違い 5)年次有給休暇とその他の休暇 3.毎月変動する手当の計算方法について(支給項目) 1)割増賃金の法的ルール 2)割増賃金の計算 3)欠勤控除の計算(ノーワークノーペイ) 4)減給の制裁の計算 5)通勤手当の課税・非課税 4.社会保険料・所得税・住民税について(控除項目) 1)社会保険制度のしくみ 2)入退社時の社会保険料控除 3)産休・育休時の社会保険料免除 4)所得税の計算方法 5)住民税のしくみ 6)その他の控除 5.給与の計算ロジックを理解しよう(演習問題) 1)給与計算問題 2)演習問題解答(給与) 6.賞与計算のポイントと手順(賞与計算) 1)社会保険料の計算 2)雇用保険料の計算 3)所得税の計算 7.賞与の計算ロジックを理解しよう(演習問題) 1)賞与計算問題 2)演習問題解答(賞与) 【第4講】 1.グランドデザインとして人事戦略を定める 1)変化を可視化するために人的資本という概念を生かそう 2)市場対比と確定した未来を可視化する 3)運用の実際をヒアリングし事実として整理する 4)可視化された現状をもとに課題優先度を判断する 5)人事ポリシーを定義する 2.等級制度を体系化する 1)会社として従業員に求める等級軸の選択肢 2)人材ポートフォリオとしての整理 3)管理監督者の区分 4)等級定義の明確化:職務等級設計 5)等級定義の明確化:発揮行動等級設計 6)昇格・降格ルールの設定 3.報酬を総合的に整理する 1)報酬構成の設計 2)月例給与のレンジを定める 3)わかりやすい給与改定ルールを定める 4)役職など職務にかかる手当を設計する 5)定期賞与ルールを定める 6)報酬ポリシーとして整理する 4.評価制度を基準とコミュニケーションで整理する 1)評価制度の全体像を定める 2)評価プロセスとして評価期間と評価者を定める 3)個人業績を目標管理制度で評価する 4)行動評価基準を設計する 5)報酬及び昇格判断への適用ルールを定める 5.採用から代謝(退社)までのフローを定める 1)必要な人材が残るようになっているかフローで判断する 2)求める人材像をより具体的に定め採用基準とプロセスに落とし込む 3)採用後のオンボーディングを徹底する 4)定年と再雇用に対応する 6.移行措置を定め丁寧な浸透を図る 1)原則不利益変更はないように移行設計する 2)社内承認を経て規程化する 3)説明会と質疑応答を準備する 7.企業文化として定着させる 1)評価者教育を徹底する 2)制度改革の効果を定点観測する仕組みを用意する 3)情報発信を継続し改革を止めない ※年間ガイドからプログラムが変更となりました。
受講料
SMBC経営懇話会 特別会員
税込 110,880円
SMBC経営懇話会 会員
税込 126,720円
それ以外の方
税込 146,520円