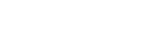来場セミナー
グループ経営の基本と諸制度、今日的課題と実務ポイント
グループ経営実務マスターコース【全3日間】
~経営管理・構造改革と企業再編、M&A(企業買収)の基本~
日付
会場案内
※受付は30分前より開始いたします ※欠席・遅刻の場合は、必ずご連絡をお願いいたします ※会場は当日1F掲示板にてご確認ください ※コース申込の場合は、割引適用価格となります ※コース申込の場合は、一部日程のキャンセルはできかねます ※各講(1日単位)ごとにお申込いただけます(各講のセミナー詳細よりお申込ください)
概要(狙い)
昨今、企業経営とは子会社・関連会社を含めたグループ全体で、戦略策定、推進、管理することが標準となっており、企業規模も大企業に限らず幅広くグループ経営が浸透してまいりました。そこで、グローバル化や事業のリストラクチャリングなど、企業を取り巻く環境が大きく変化していく中で、グループ全体による迅速かつ的確な経営判断と、そのための構造改革が求められております。 また、グループ事業再編においては、M&Aの積極的な活用も行われており、さらに、グループ経営をめぐる法律や会計・税制度は、改正がめまぐるしいとともに、判断しにくいグレーな部分も多く、こうした戦略や制度とリスクをしっかりと把握し機能させていくことも重要な課題と言えます。 本コースでは、グループ経営に係る重要な視点を3つの講座で構成しており、基本的な考え方から最新課題を踏まえた実務ポイントまで、各々の専門家により解説していきます。
対象者
経営企画、関連事業、法務、財務、内部監査部門等担当者
講師

株式会社日本総合研究所
リサーチ・コンサルティング部門 理事
山田 英司 氏
略歴:早稲田大学法学部卒業、英国国立ウェールズ大学経営大学院でMBAを、EUビジネススクールでDBAを修了。事業会社のグループ経営管理部門を経て、現職。グループ経営、M&A、ガバナンスなどのコンサルティングに従事するとともに、ベンチャー企業のCFOや監査役、大手企業の社外取締役を歴任。
著書:「ボード・サクセッション」、「スキル・マトリックスの作成・開示実務」(ともに中央経済社)、「グループ・ガバナンスの実践と強化」(税務経理協会)

公認会計士・税理士
太田 達也 氏
略歴: 昭和56年慶応義塾大学経済学部卒業。第一勧業銀行(現 みずほ銀行)勤務を経て、昭和63年太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所。現在、豊富な実務経験・知識・情報力を活かし、各種実務セミナー講師として活躍中で、複雑かつ変化のめまぐるしい会計及び税実務のわかりやすい解説と、実務に必須の事項を網羅した実践的な講義には定評がある。また、多数の書籍の執筆および雑誌等への寄稿を積極的に行っている。
著書: 「会社法決算書作成ハンドブック」(商事法務)、「減損会計と税務」「商法決算ハンドブック」「外形標準課税実務ハンドブック」「金融商品の会計と税務」(中央経済社)、「消費税「インボイス制度」完全解説」「決算・税務申告対策の手引」、「「自己株式の実務」完全解説」「「解散・清算の実務」完全解説」「「収益認識会計基準と税務」完全解説」(税務研究会出版局)、他多数。
プログラム
【第1講】グループ会社の経営管理と構造改革 1.グループ経営とは何か 1)企業経営を取り巻く環境の変化 2)グループ経営の必要性 3)グループ経営のフレームワーク 4)グループ経営の目指すべき方向 5)グループ経営推進に必要な要素 2.グループ経営の基本構造 1)グループ経営を支える組織構造 2)グループ経営における組織形態と各制度の比較 3)グループ本社に必要な機能 4)グループ会社の分類とミッション定義 5)最適なグループ会社の構成 3.近年のグループ経営課題 1)グローバル化への対応 2)経営戦略の実現のためのM&A 3)グループ・リスクマネジメント 4)サステナビリティへの対応 4.グループ経営の強化に向けて 1)事業・機能の強化と効率化 2)コーポレート組織の改革 3)事業再編の実施 4)グループ経営におけるシナジー追求 5.グループ経営管理のあり方 1)経営管理におけるサイクル・指標と当事者 2)評価指標の選定 3)グループ経営における業績評価 4)事業部門の評価方法に関する論点 5)グループにおける人材マネジメント 【第2講】グループ企業再編の法律と会計・税務 1.グループ企業再編の法律(手続概要)と長所・短所 1)組織再編に係る法制度の整備と最近の動向 2)再編諸手法の手続概要および長所・短所 3)合併 4)会社分割 5)株式交換・株式移転 6)諸手法の分類と比較、長短 7)事業再編の活用方法とポイント 2.事業再編と税務上のポイントを押さえる 1)企業組織再編税制の基本的な取扱い ●基本的な課税の仕組み ●みなし配当課税の問題 ●株式譲渡益課税の問題 ●移転資産に係る譲渡益課税の問題 2)適格組織再編成の2類型 ●企業グループ内の適格組織再編 ●共同事業を行うための適格組織再編 3)適格要件の具体的解説 3.各再編手法別の税務 1)合併 ●適格合併の場合 ●繰越欠損金の引継ぎ制限と使用制限 ●特定資産の譲渡等損失に係る損金算入制限 2)会社分割 ●適格分割の場合 4.最近の税制改正の内容と活用(スピンオフ税制、パーシャルスピンオフ税制等の創設) 5.企業結合・事業分離等会計基準の会計処理のポイント 1)パーチェス法の会計処理 2)のれんの会計処理 3)共通支配下の取引に係る会計処理 〈1〉親会社と子会社の合併 〈2〉子会社間の合併 6.活用事例 1)合併と不採算事業の整理 2)無対価合併の事例 3)赤字子会社の救済と繰越欠損金の引継ぎ制限・使用制限 4)グループ企業の含み損資産の活用と繰越欠損金の引継ぎ制限・使用制限 5)会社分割とMBO 6)完全子法人の整理と適格現物分配の活用 7)会社分割を活用した一部事業の身売り事例(M&Aの事例) 8)その他 【第3講】M&A(企業買収)の基本と実務ポイント 1.M&A戦略の全体像 1)M&Aのトレンド 2)買収における陥穽 3)買収戦略における課題 4)買収戦略の全体像 2.M&A(買収)戦略の策定 1)買収戦略の位置づけ 2)企業戦略との関係 3)戦略策定における役割分担 4)ターゲット企業の抽出 3.M&A(買収)戦略の推進 1)一般的な買収プロセス 2)デューデリジェンスの重要性 3)買収スキームの検討 4)企業価値の算定 5)買収条件の設定 4.PDM/PMIの施策推進 1)PDM/PMIの位置づけ 2)企業買収におけるPDM 3)推進の全体像 4)企業買収におけるPDMの視点 5)PDM推進の留意点 5.M&A(買収)対応基盤の構築 1)基盤構築の重要性 2)組織体制の整備 3)推進プロセスの標準化 4)モニタリングプロセスの標準化 6.その他の近年のトレンド 1)グローバル対応 2)サステナビリティの考慮
受講料
SMBC経営懇話会 特別会員
税込 89,100円
SMBC経営懇話会 会員
税込 103,950円
それ以外の方
税込 118,800円